
こんにちは!nemu(@nemusblog)です。
今回、27歳から約2年半働いた今の組織を離れ、別の進路に進むことにしました。自分への気持ちの整理や、周りから「なんで辞めるの!?」と聞かれることもあり、ここでまとめておきたいと思います。
ポストが見つからないとか、上司が合わなかったというわけではなく、チームも同僚にも恵まれ、いろんな機会もあった中での自主的な選択なので、こんな人もいるよという感じでn=1としていただければと思います。国連に入るための情報は多いですが、離れた人たちの情報は多くなく、でも入職には相当な努力が必要な分、いろんな意見を出すことには意味があるのかなと思い投稿することにしました。
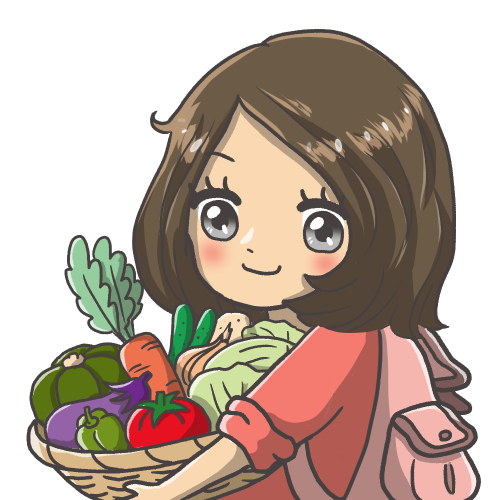
と言っても、検索すると意外とたくさんの人のエピソードを見つけることができます。組織的な課題はそこでカバーされていると感じたので、私からは省きます。
また、国連で働くことは18歳頃からの目標で、当時も、その後も「アフリカの子どもの栄養支援がしたい」思いだけを軸に目指した道でした。ご経験豊富な先輩方からすると、未熟な部分もあるかなと思いますがご了承ください。私がP2(エントリーレベル)で経験が少ないということも、下記の考えに至った理由かなと思っています🌱
Contents
1. 課題に「携わる」ことで満足するのではなく、解決できる人材になりたかった
どこの組織でも言えることですが、多くの人は組織の決めたことに従って働き、本質的な変化を起こしていけるのはほんの一握りではないでしょうか。
特に国連は、多くの人が入ることを「目標」「憧れ」としている分、入った後は残ることに注力する人が多く、異なるアプローチやアイデアに挑戦する機会は必ずしも多くないと感じました。特に20代は2%以下、平均入職年齢は35歳を超えると言われる組織では、若者は組織がやっていることに関わり、そこで価値を出していくことで精一杯になってしまう印象です。
組織の中で価値を出していきたいキャリア人生ならそれも良いですが、「組織に属する」ことが目標だったわけではなく、肩書や昇格に魅力を感じなかった私は、ここでまず立ち止まってしまいました。
最初は、ずっとやりたかったことに自分が携われていることが心から嬉しく、満足していました。でも、これは自分じゃなくても誰かできる。自分は(特に下の役職のような)代わりがいる仕事に「携われている」ことで満足したかったのか。まだ挑戦できる年齢だから、どうやったらこの課題をより良い形で解決に繋げることができるのか一歩離れて考え直してみても良いのではないか、と感じるようになりました。
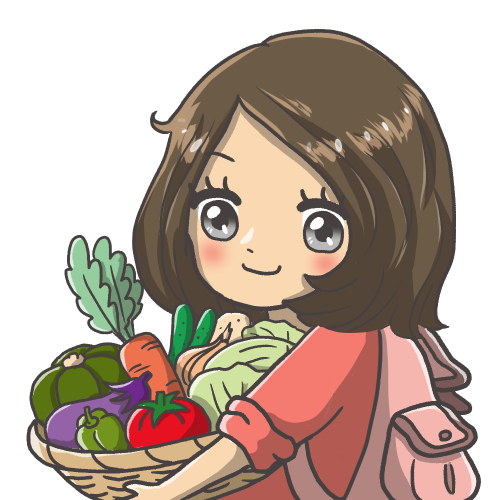
もちろん努力次第で自分らしい価値も出していける、というのはどこでも当たり前ですが、他と比較すると構造上よりChallengingだな、という私の個人的な印象です。
他の発信でも出ていた話ですが、残るために根回しや調整に動く人たちを私も組織内外で見ました。私は国際協力(少なくとも栄養改善)は支援が必要なくなることが一つのゴールだと現段階では思っているので、「課題を解決したい」と「自分は残りたい」は相反しているのではというジレンマを感じることもありました。様々な考えがあって良いと思うのですが、私はまだフレキシブルに動ける間に、もっと多様な価値観に触れたいと感じるようになりました。
2. 今ならまだ「せっかく得たもの」を手放す勇気があった
2年目の頃、個人コーチングで今後の理想の人生を描く時間がありました。1つは、組織で上に上がっていくこと。もう一つは、プライベートとのバランスを取って(結果的に次決まっている)別の進路に進むこと。
前者はタイミングと運があればこうなるだろう、をすぐに描くことができました。でもなぜか心が全然わくわくしなかったのを覚えています。
数年働いていくつか選考に通過するようになると、自分の行けそうな国、働けそうなポストがだいたい見えてきます。きっと次に仏語Non-family duty stationのP2かP3に短期契約で行って、そこからまた別の契約を繋いで、、これくらいの年齢でこのポジションだろうな。また1から人間関係を作って、想定されるこんな業務やカオスを乗り越えて。仕事は楽しいし、相変わらず「国連職員であること」がちょっと誇らしい。
でも、その分パートナーには待たせるか付いてきてもらうかしないといけない。家族を持つことも遅れるかもしれない。そうしているうちに、組織を手放しづらくなって、良い生活にも慣れてしまって、、きっと周りからしたらそれが正解なのかもしれないですが、私はなんとなくぴったりはまりませんでした。
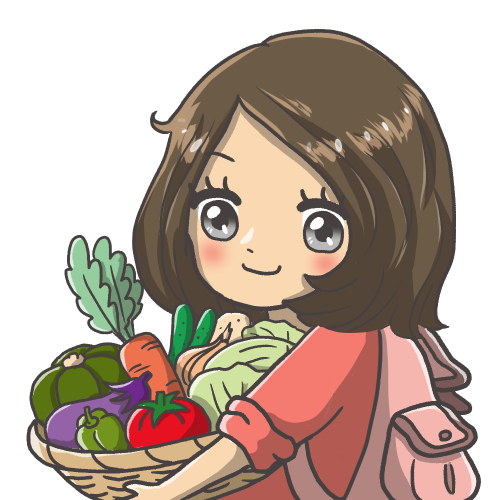
大学の頃、部活の関係で旧帝大の友人が多くいました。全力で受験を乗り越えて「〇〇が好きでもっと学びたくて」「将来は地元で先生に」と言っていた友人たちが、就活期に揃いに揃って5大商社に入り、最近会うと遊びやステータスの話ばかりになっていて、私はちょっと寂しかったです。全然良いし、そういう人の方が多いのかも知れないですが、私はそこに違和感を感じてしまう人間でした。
「安定」や「せっかく得た」レールに乗ると、それを手放すことが惜しくなり、時に「自分が本当に望んでいたこと」から離れてしまう事があるんじゃないかと思います。
それを、ステータスや給与で補い、これで良かったんだと自分に言い聞かせる人生を送り、、たくて努力してきたわけではないです。残るために担当分野を変えることなどもあるあるですが、好きじゃない仕事をするためなら、わざわざここまで来てないです。心からこの仕事が好きで、「やりたくて」やっているからこそ、そこからズレてしまわないよう、自分に正直でいたいし、それを得れる人材になる努力を続けたいと思っています。
3. 現場との距離が離れていく気がした
国連は現場と遠い、というのは経験者なら皆様ご存知だと思います。現場が好きならなぜ国連、との声もありそうですが、NGO時代に助けられない子どもを目の前にして、「もっと根本から栄養制度を改善したい」「政府と働けるのは国連だ」と思い目指したこともあり、この5年間のキャリアの中で現場側と政府側両方に関われたのは結果的にMore than happyでした。
でも、私は国連職員に多いエリートコースではなく、バックパッカーやヒッチハイカーとして世界を旅して、途上国で人と話す中で国際協力を目指したことが原点だったので、国連職員の生活水準の高さとのギャップは最後まで慣れませんでした。
 【21歳女子大生】世界一周に、留学、農家ステイ、バックパッカー、インターンを全部詰め込んだ話。
【21歳女子大生】世界一周に、留学、農家ステイ、バックパッカー、インターンを全部詰め込んだ話。
国連職員の生活水準の高さについては、こちらの動画でも話されています。
例えば、国連オフィスの近くに、掘っ立て小屋の小さいローカル料理屋があるのですが、私以外食べている外国人スタッフは2年半でほとんど見かけませんでした。ごく少数ですが、そんなもの健康に悪いよ、と言われたこともありました。いつも私が買い物しているローカルマーケットに同僚を連れて行くと、マスクをして「汚すぎるから早く出よう」と言われたこともありました。現地の生活を知らずに良い仕事はできないと思ってしまう私は、まだまだ夢見がちなのかもしれません。
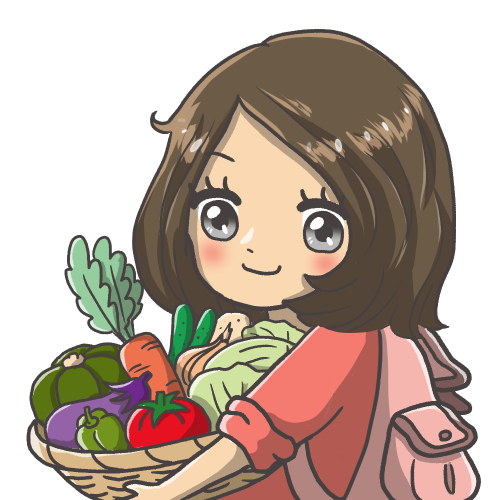
国連職員はそういうものなのかもしれません。でも、私はこの道を目指したきっかけが旅やボランティア活動、現地での交流だったので、しっくりこない部分がありました。
私はJPOとして来る前にも同じ国に2度住んでいたので、入職時から現地語や現地食には詳しかったのですが、それに対して現地スタッフたちがとても驚いていて。なんでそんな驚くの?と思っていたのですが、数ヶ月経って、国連オフィスではそれが珍しいことに気づきました。
次のキャリアのために今この国にいるだけだ、と思われたくなくて(意地?笑)この2年半で国内をたくさん訪れ、誰よりも詳しくなれたのはいい思い出です。
4. 業界が厳しい中で、自分はまだ他のチャンスを掴める立場だと思った
最近報道でもあるように、アメリカの影響で国際支援業界は資金難に直面しています。国連職員のリストラや統合といった話が出ているのも、皆様ご存知かと思います。
そんな状況において、海外で働きやすいスキルや国籍を持っている人は選択肢も多いので、皆リストラ危機にある場合ではその制約がより多い人が機会を得るべきだと感じたことも、この決断を後押ししてくれました。確かに外国人スタッフとして持って来れるものも多いけれど、外国人スタッフ一人の給与で自国スタッフを何人も雇える中、組織が厳しい状況で残す意味は相当のものがないと、と感じることが多々ありました。
家族を守りたい気持ちも子どもに良い教育を与えたい気持ちも皆同じ、且つ圧倒的に若い私は、自分のためにキャリアを諦めたパートナーも子どもも抱えておらず、もらえる国連年金もありません。他でもチャンスを得やすく動きやすい私が他の選択肢に目を向けるのはすんなり腑に落ちるところでした。
またアフリカだと、家族の誰かが国連で働いているとなるとそこに家族や親戚が経済面を委ねてる場合があったりします。教育機会が豊かな日本で育った私の何十倍もの努力をして、そんな家族の期待もあって、そんなのは私はどれだけ理解しようと努めても想像しきれないので、そこで私を残してほしいと動く気持ちには、、なりませんでした。
UN80を含め、今後数年はより多くの変革が予想されます。これは自戒であり、反省でもありますが、日本語で得やすい前向きな情報ばかりでなく、組織がどうなっているのか、どこに行こうとしているのか、それは本当に自分自身が関わりたいことなのか、を考える必要があると感じています。
5. どうしても「ドナー国」が強くなる構造の中で、自分がどんな国際協力をしたいか一旦離れて考え直したかった
以前は「途上国」「アフリカだ」と見ていた地図の端っこの国が、自分の一部になっていく中で「発展って何を目指してるんだっけ」と思うことが、正直何度かありました。こっちの生活に慣れていく中で、Global Northの枠組みに沿って「足りない部分」を埋めるような事業(もちろんそんな事業ばかりではありません&国連だけでなく国際協力全体での話です)は本当に現地の人々のためになっているのか、時には自分の仕事がただの自己満足のように感じられることもありました。いや援助って結局は自己満、、そんな話は一晩くらいお酒を交わしながら話したいので、ここでは省略します。笑
特に国連はドナー国の影響が強く、その国籍を持っていること・教育を受けていること・その国で求められていることを知っていることがどうしても働く上でプラスに働きやすい構造だと感じることもありました。そんな中、レポートを書いて資金を得る(そして自分のポストを確保する)ための作業か、本当に現地の人のためになる介入か、わからなくなることがありました。
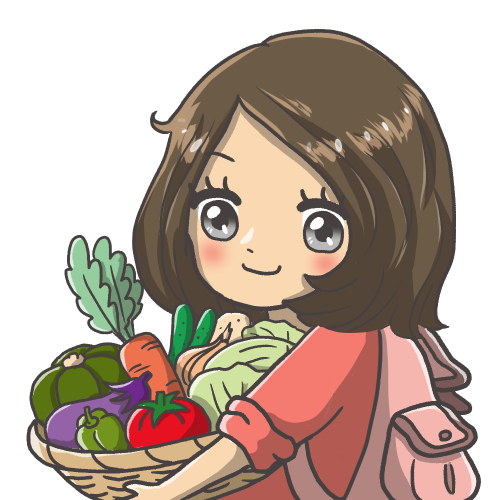
「援助の機会が増えて喜ぶ人間にはなりたくない」というある先輩の言葉がとても印象に残っています。
ドナー国で評価されるレポートと、現地の人たちの役に立っているかは、時にベクトルが違ったりもしました。この世界は、まだ植民地主義的な構造の延長線上にあるようにも感じました。
そんな大きなことに、私は何もできないのですが、でも何も知らずに「貧しい国を助ける」みたいなことに憧れていた自分に喝を入れて、もっとちゃんと勉強したいなと。それはこんな経験をさせてもらった自分の使命だとも思っています。
6. キャリアだけでは、これ以上幸せになれないと思った
希望のキャリアを歩めて満足した今、これ以上の成功(=今のところ見つかってない)を追いかける忙しい日々よりも、自分の幸せを追い求める人生に挑戦してみたくなりました。
もちろんキャリア構築も自分の幸せに大きく貢献してくれたのですが、タイミングや運が全てのこの業界で「確実」はないし(その割に必要な努力や犠牲は多い)、全てが最高に良い環境で働けた今、これ以上は今のところもう思いつかなかったです。
今以上の満足度を得るには、キャリア以外のプライベート面を充実させる必要があると感じたのと、キャリアにおいても組織やこの仕事に「私にしかできないこと」を持ってこれる人材になることが必要だと感じました。
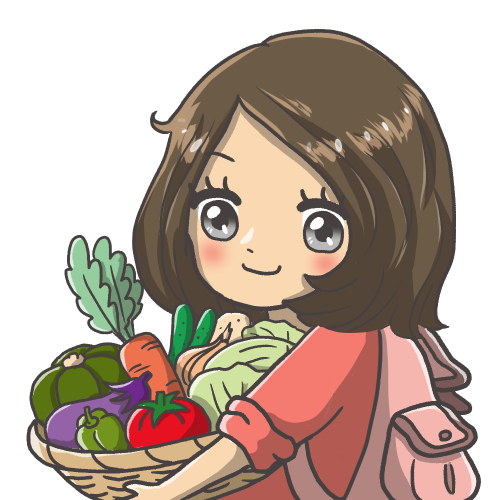
例えば私達は日本人だから、ドナー大国として日本関連のお金を持ってくる事は「私がいたからできる」大きな成果にもなる。さっきの残す云々の話でも、お金を引っ張ってこれるなら残す価値はある。でも、私は国際栄養が好きでこの仕事をやってるから、できれば私の国籍や「ドナー国だから」持っているコネクションではなく、私の好きな専門分野で役立てる人になりたいと感じています。ここにおいては、その姿をずっと背中で見せてくれた私の直属上司のおかげで気づくことができました。
こうやって「私にしかできないこと」とか言ってるのも、もしかしたら夢見がちなのかもしれません(これもお酒飲みながらどなたか、、!笑)。でも、私じゃなくてもできる仕事のために、私しか経験できない幸せを犠牲にはできないとも思います。
例えば家族を持つことや、誰かと一緒に生きること。大切な友達との関係もそう。この仕事は働き方が特殊故にそのあたりでは苦労されている方が多かったです。国際協力の求人は毎日山程出ていますが、娘や友人、パートナーとしての私に代わりはいないので、もう少しそのバランスを大切にしていきたいなと思いました。
人間関係においても、人気の移住先ではない西アフリカで出会った人は、大部分は「仕事で言われて来た」人たちでした。任期が終わればどんどん入れ替わるし、少なくとも「好きで来た」人は多くはない中で、その場しのぎになりがちな関係構築はちょっと寂しく感じることもありました(だからこそ、仲良くなりたいと思える人達に会えたときはとても嬉しかったです)。
今回の国は好きだったから良かったけど、縁もゆかりもない国で、そんな人間関係を毎回構築しながら数年毎に異動を続けるほど、昇格していきたいわけでも、組織にしがみつきたいわけでも私はなかったようです。
特に20代はずっとこんな異動ばかりで、そろそろそんな生活への飽きと、腰を据えて生活することへの憧れが出てきたのもあります。時間をかけて構築した大切な人間関係がそばにあってほしいし、同じ国で季節を何度も過ごしたいです。
これが、私に家計を委ねるパートナーがいて、子どもがいたら、また全然違ったと思います。自分の好きとか関係なく、家族のために仕事を続けていたかもしれません。でもそうではないので、これをプラスに捉えてまた新しい一歩に挑戦したいと思っています。
これから目指す方に
私はこの仕事(国際栄養)のキャリア構築を、成功も失敗も含めてシェアして誰かの参考になれば、と思いSNS発信をしているからこそ、目指す人の多い職場を離れる、という経験を共有をすべきか悩みました。ただ、もし私自身がこう思うことを事前に知っていたら挑戦しなかったか、というと絶対そんなことはないです。ネットの誰かの話を聞いて辞める程度の目標なら、そもそも叶わないとも思います。
離れた理由の記事なので、こんな内容になってしまいましたが、憧れたけれど違ったわけでも、同僚や上司に幻滅したわけでもありません。日々やりがいに溢れ、他では出会えない素敵な先輩方や優秀な同僚と働き、たくさんの海外出張に恵まれて本当に充実した日々でした。これ以上の仕事は、今のところ私は見つけていません(なので、先数年は働きません!笑)。
ただ、私は国連に入りたくて専門分野を選んだわけではなく、アフリカの子どもの栄養課題を解決したくて、その過程で今の組織があったので、もう少し自由な今組織を出て挑戦してみよう、一歩離れて色々考えたいな、と思って飛び出す次第です。
今はタイミング的にもこの業界は厳しく、それに振り回されるより、その期間専門性の向上に充て、また落ち着く頃に戻ってこれたらと感じているところもあります(とか言いつつ、もっと他のPriorityができたら、それはそれで楽しみです💓)。なので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします!
最後に
働いていた頃、コーチングで「一番心が動いた瞬間は?」に対して「憧れた仕事ができていること」以外答えられなかった自分に違和感を感じたことがありました。大きな会議に出て、難しい議論をまとめたり、予算を取ってきたり、インパクトが大きいことはたくさんできたと思います。面接で語れるような成果は重ねてきたけれど、私の心が動くのはそういったことではなかったようです。
それは、これまでの仕事や旅で出会ったたくさんの人との珠玉の経験があったからで、今振り返るとそんな自分の感覚は好きだなと思ったりします。また、そんな人達との出会いが私をここまで連れてきてくれたので、これからもそれを無駄にせず、ずっと努力を重ねていきたいです。
挑戦し続けるほど、人生は楽しくなると信じています。何年も憧れた夢を掴み、そこで新たに出会った価値観を信じて、もっと人生を充実させていきたいです。🌸
ちなみに、次はどうするの?と聞かれますが、退職後まずはスペインの巡礼を歩く予定です!Buen Camino!
*
今回は多くの方に届けたく、既に発信している内容は省いてしまいました。これ以外にも、プライベートとの両立やその他の葛藤もありました。良ければ下の過去記事も読んでみてください! 🌱
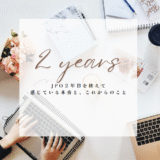 JPO2年目を終えて感じている本音と、これからのこと
JPO2年目を終えて感じている本音と、これからのこと
 「早く入れば両立できる」と思っていた新米国連職員が、女性のキャリアとプライベートの両立について思うこと
「早く入れば両立できる」と思っていた新米国連職員が、女性のキャリアとプライベートの両立について思うこと

